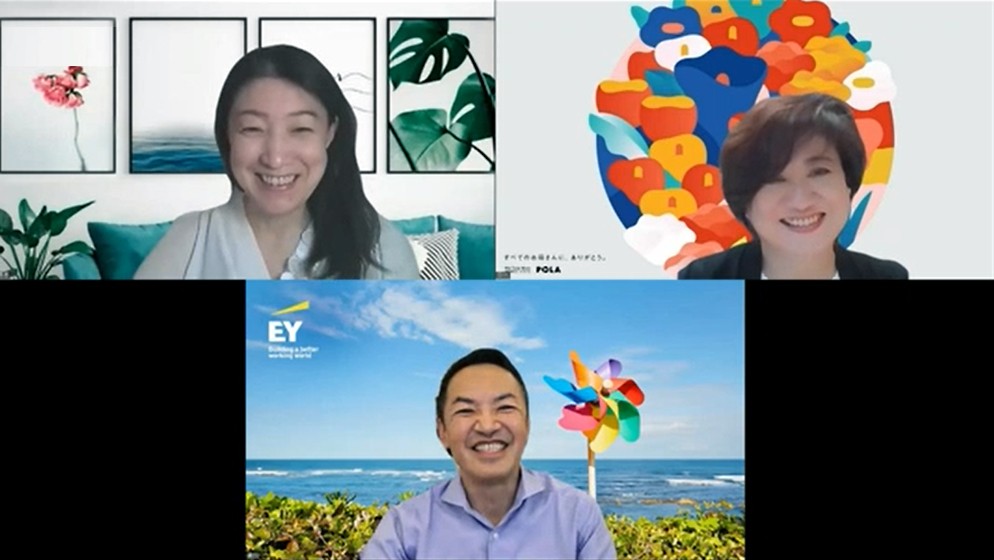塚原 月子氏(以下、塚原氏):今回の対談では、ポーラの及川さんから女性として経験されたチャレンジ、貴田さんからはご自身のセクシャリティに起因した差別経験なども伺いながら、ダイバーシティ&インクルージョンに対して一個人として、またマネージャー層として、具体的に何ができるかを考えたいと思います。では、お二人の考え方や自分らしくあって良いと思えるようになったきっかけをお聞かせください。
及川 美紀氏(以下、及川氏):私の場合は常にジェンダーがついて回るのですが、最初に自分らしさを出しきれなくなったと感じたのは出産前後です。やむを得ず時短勤務を選び、皆と同じ働き方ができないと悩んだ末に萎縮してしまい、ジェンダー+母親で自分の殻に閉じこもってしまった経験があります。
もう一つは、部門長になり役員になって会議に出ても、特に、社外において「紅一点」と言われ続けたこと。その居心地の悪さから、自分の発言が私個人の意見なのか、それとも女性代表なのかに惑いが生じ、他者の理想の答えを探している自分に気付いたこともあります。
塚原氏:そこからどのような強い意志を持って抜け出されたのですか?
及川氏:強い意志があったというよりは、紅一点である前に及川という個人の存在を明らかにしていくことが大事だと突然行き当たりました。当時は40代前半でしたが、その年代の社会人が普通に抱く感情や疑問をどんどんディスクローズしたんですね。そういうときには必ず、マイノリティである私の思いや意見を聞こうとする人たちが現れてくれました。振り返れば、ディスクローズしようとする自分と、周囲の方々の受け入れの両方があって壁を越えられたと思います。
塚原氏:貴田さんのご経験も教えていただけますか。
貴田 守亮(以下、貴田):仕事に就いて25年以上のキャリアになりますが、ありのままの自分を意識するようになってからまだ10年もたっていません。海外で育ち就職し、自分がアジア人でゲイであるというダブルマイノリティの期間が長かったからです。どんな会議に参加しても、さまざまなチームの一員としても、まずは自分自身が周囲に受け入れられているかを心配し、常にマジョリティ側の視点に配慮しながらキャリアを積んできました。
ところが6年前に日本に帰国して、突然アジア人であるマイノリティ性が消えたのです。しかも男性なので容易に意見を聞いてもらえる状況になり、すごいカルチャーショックを覚えました。自然体で意見を聞いてもらえるということはマジョリティの特権だったのではないかと気付いたのです。
塚原氏:日本人の中に入っただけでそれほど立場が変わったのですか?
貴田:マジョリティ性とマイノリティ性がどういう特性かは、定義や立場によって変わりますし、実は皆さん両方持っていると思います。ただ、マジョリティでいる方々でマジョリティ意識を持つ方は皆無に近いので、特権と考える機会もなければ、主張している自覚もないでしょう。しかし、マイノリティ側は、そこに特権がある事実を毎日感じているのです。