
気候変動の議論は科学的な視点から

高瀬氏は気候変動を巡る議論ではいまだに懐疑論が横行しているとし、「まずは信頼できる科学的エビデンスにあたることが大切です」と解説します。現在、気候変動がどのような状態にあるのかについては、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)によるレポートが参考になります。最新の6番目のレポート(AR6統合報告書)では、査読付き論文を根拠とした物理的科学基盤がまとめられています。
日本国内においても科学的な観点から、気候変動の影響や適応・緩和の現状を測定する試みは行われています。茨城県つくば市の国立環境研究所がまとめたIPCCレポートの要約を見ると、温暖化は人間の活動によって産業革命時代から既に1.1℃進んでいます。その被害は途上国や困窮層において顕著で、高瀬氏がCDPジャパンにいた頃のインドでは、「毎年100人規模で暑さによる死者が出ていた」と言います。
今後10~20年以内に気温上昇が1.5℃に達する可能性は高いと考えられています。さらなる上昇を食い止めるためには、脱炭素や再生可能エネルギー(再エネ)普及の取り組みを加速させる必要があります。高瀬氏は、既に欧州や中国、インドなどでは再エネに取り組む動きが活発化していると話します。
日本においては気候変動に関して、革新的技術開発にて解決という論調が強いですが、既に存在する技術でも大幅に対策を進めることが可能であるという認識が不足しています。再エネは既に化石燃料よりも安くなっています。こういった既存の技術を普及させるためには、政策やガバナンス、ファイナンスなどの社会システムや制度による対応が必要ですが、日本はガバナンスが弱い状態であり、やっと電力会社の不正閲覧などが表面化するようになってきましたが、まだまだガバナンスを強化する必要があります。
「企業のちょっとした努力や、家庭で小まめに電気を消しましょうという話ではなくなっています。2050年までにカーボンニュートラルを達成するためには、新しい社会構造やビジネスシステムへの移行が不可欠です」
気候変動関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)による「気候変動は金融リスクであり、ビジネスチャンスでもある」という新たな捉え方は、社会変革に向けた潮流の代表的な動きと言えるでしょう。
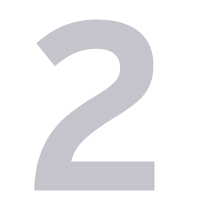
“コスト負担の大きさ”は”影響力の大きさ”に転化しうる
あらゆるビジネス活動にはCO2の排出が伴い、出張のフライトも例外ではありません。高瀬氏が過去に勤めていたCDPジャパンでは、職員一人一人にカーボン・バジェットを定め、CEOも「遠くへの出張は年に数回まで」と公言していたそうです。NGOと営利企業とでは導入へのハードルも異なるとしても、機関投資家が気候変動に関する取り組みの開示を求める中で、営利企業にもそうした取り組みは広がると予想されます。
サステナビリティ事業に関する公的な制度整備も進められており、高瀬氏は脱炭素事業の枠組みとしてスコープ1、2、3を紹介しました。日系企業においても、化粧品大手が2050年までのバリューチェーン全体のネットゼロを宣言するなど、積極的な動きが見られます。
こうした話を受けて受講者からは「バリューチェーン全体のネットゼロを目指す上で、どこまでが自社の責任になるのかは定量的な測定が難しいのではないか。また、サプライヤーの提供サービスについて、複数企業のスコープ3がオーバーラップする可能性があるのではないか」という鋭い指摘が投げかけられました。
高瀬氏は「スコープ3はオーバーラップするものである」と回答した上で、「関係企業の全てが主体的に取り組む仕組み作りが必要であり、それこそがスコープ3である」と回答。ネットゼロに向けた国際的戦略の一つである、科学的根拠に基づく目標(SBT)の枠組みについても、そうした狙いがあると言います。
「スコープ3においては、物流や自動車業などサプライヤーを広く有する企業ほど負荷が大きくなり、業種による不平等を感じることもあるでしょう。しかし、“負荷の大きさ”を“影響力の大きさ”と捉え直し、ビジネスチャンスとして肯定的に取り組む姿勢が確立されつつあることは、国際的な追い風と考えられます」

日本には再生可能エネルギーの資源が豊富に存在する
高瀬氏は日本の再エネ事業について、「利用に対する企業のコミットメントが世界でもトップレベルでありながら、政府による目標設定は消極的」と言います。そもそも自然エネルギー電力のシェアは2020年時点で約20%に過ぎず、英国・ドイツなどの進んでいる国と比べると2分の1にも達していません。
「『このまま再エネが手に入らない状況が続くなら、工場は日本国外に移転せざるを得ない』と考える企業が増えています。2030年の自然エネルギーのシェア目標を日米で比較すると、日本は36~38%と見積もる一方、米国は80%以上に向けたシナリオを公表しています」
自然エネルギー財団は独立したシンクタンクとしての立場から、自然エネルギーの利用を政府に提言していると言います。2023年4月に公表した* 自然エネルギー財団「2035年エネルギーミックスへの提言(第一版)」では、太陽光発電と風力発電を軸に80%のシェア率まで引き上げることを提案しています。
「日本には利用可能な自然エネルギーが少ないというのは大きな誤解です。再生エネルギー先進国であるドイツの大臣が『日本はなぜ洋上風力にもっと積極的に取り組まないのか』と驚きをあらわにするほど、導入する余地は十分にあります」
高瀬氏は、周囲を海に囲まれた日本において特に期待がかかるのはフロート式の洋上風力だと言います。自然エネルギー財団を含む世界中の専門家が、変動性再生可能エネルギーが大量導入された際、どのように対応できるのか、つまり系統を広域で運用したり、需要側が発電に合わせたり(デマンドレスポンス)、蓄電池を活用するといったことがどの程度必要なのか、どのように運用したらいいのか、について検討をしています。太陽光発電が発電しない時には風力が発電していることが多いですが、両方が止まった時にはどうするか、といったことも考慮した上で、100%再エネで供給することも夢ではないと言います。
産業革命前からの気温上昇を1.5℃以内に食い止めるための時間的な余裕はないことがわかっています。高瀬氏は、社会全体が気候変動対策について公正に取り組むために、「開示が一般化し、ガバナンスの精度が担保されることで不正に対する自浄作用が働くこと」「科学的な根拠に基づいた議論を行い、利権による硬直化を防ぐこと」が今後の国際情勢のスタンダードになってくると指摘しました。
*自然エネルギー財団「2035年エネルギーミックスへの提言(第一版)」、www.renewable-ei.org/activities/reports/20230411.php(2023年7月4日アクセス)
サマリー
気候変動に関しては、科学的な認識から問題を正しく認識し、社会の枠組みから変えていく取り組みが必要です。温暖化は現在もなお進行しており、バリューチェーン全体でネットゼロを目指していかなければ国際的な目標は達成できません。日本においては自然エネルギーのシェア率をより高めることが求められています。





