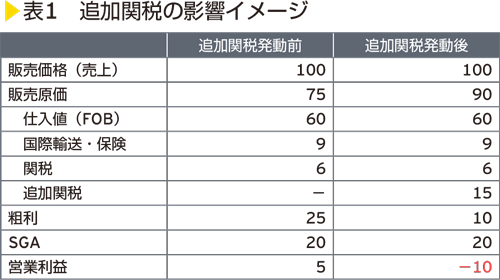EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
EY | Assurance | Consulting | Strategy and Transactions | Tax
About EY
EY is a global leader in assurance, consulting, strategy and transactions, and tax services. The insights and quality services we deliver help build trust and confidence in the capital markets and in economies the world over. We develop outstanding leaders who team to deliver on our promises to all of our stakeholders. In so doing, we play a critical role in building a better working world for our people, for our clients and for our communities.
EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide services to clients. For more information about our organization, please visit ey.com.
© EYGM Limited. All Rights Reserved.
EYG/OC/FEA no.
ED MMYY
This material has been prepared for general informational purposes only and is not intended to be relied upon as accounting, tax, or other professional advice. Please refer to your advisors for specific advice.