
会社法と金商法の交錯における監査役と会計監査人の連携
情報センサー2023年4月号 特別寄稿
獨協大学 法学部教授 高橋 均
一橋大学博士(経営法)。新日本製鐵(株)(現、日本製鉄(株))監査役事務局部長、(社)日本監査役協会常務理事、獨協大学法科大学院教授を経て、現職。専門は、商法・会社法、金商法、企業法務。法理論と実務面の双方に精通している。近著として『監査役監査の実務と対応(第8版)』同文舘出版(2023年)、『グループ会社リスク管理の法務(第4版)』中央経済社(2022年)、『監査役・監査(等)委員監査の論点解説』同文舘出版(2022年)、『実務の視点から考える会社法(第2版)』中央経済社(2020年)。
Ⅰ はじめに
監査役と会計監査人は、両者とも法定監査を通じてコーポレートガバナンスの一翼を担う会社法上の会社機関です。監査役は業務監査と会計監査を行いますが、職業的専門家である会計監査人による会計監査の方法と結果については、監査役としては、その相当性を判断するものの、基本的にはその内容を尊重することとなります。また、会計監査人にとっても、会計不祥事の背景には、会社の内部統制システムの重大な不備が原因となることも多く考えられることから、業務監査の一環として、会社における内部統制システムの相当性について監査をする監査役からの情報が有益となることも多いと思われます。したがって、監査役と会計監査人は、事業年度を通じて、具体的かつ実効的な連携を行う意義があります※1。
他方で、会計監査人は、金融商品取引法(以下、金商法)上は、監査人として、財務諸表等の監査を行い、その結果は監査報告書として整理・公表されます。実務上は、会計監査人と監査人とは同一ですので、監査役にとっては、会社法上の会計監査報告が作成される時期と、金商法上の監査報告書が作成される時期の違いによる問題(「時期ずれ問題」)が存在します。いわゆる会社法と金商法の交錯ともいえる問題です。
時期ずれの問題は、2021年度3月決算に係る財務諸表から全面適用となった監査上の主要検討事項(Key Audit Matters:以下、KAM)についても関係します。
そこで、本稿では、会社法と金商法の交錯から生じる時期ずれの問題について、内部統制システムの監査に関連して、監査役と会計監査人との連携の視点から解説します。
Ⅱ 内部統制システムを巡る会社法と金商法の交錯
1. 会社法と金商法の規定
会社法においては、内部統制システムは、取締役会の専決事項として取締役会において整備の基本方針が決議されます(会社法362条4項6号)。その上で、事業報告に取締役会決議の内容と運用状況の概要を記載します(会社法施行規則118条2号)。監査役は、監査役監査報告において、内部統制システムの内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由を記載します(会社法施行規則129条1項5号)。実務上は、日本監査役協会のひな型に倣って、内部統制システムが相当でないか否かにかかわらず、内部統制システムに関する監査役の評価を記載しています。事業報告及び監査役監査報告は、定時株主総会前に株主に通知されますので、会社の内部統制システムの相当性の有無は、最終的に株主にも情報共有されることになります。
一方、金商法上は、内部統制報告書の作成が法定化されています(金商法24条の4の4第1項)。すなわち、上場会社は、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制(財務報告に係る内部統制システム、いわゆるJ-SOX)を評価した内部統制報告書を作成した上で、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けることが義務付けられています。内部統制報告書は、内閣総理大臣宛となっています(実務上は、金融庁に提出)。
2. 内部統制システム関連規定における会社法と金商法上の違い
内部統制システムに関して、会社法と金商法の規定の違いがあります。まず、適用対象会社は、会社法は単体及び親会社と子会社からなる企業集団の二本立てであるのに対して、金商法は連結ベースです(<図1>参照)。また、内部統制システムの対象領域について、会社法は会社運営に係る全てが対象となりますが、金商法は「財務報告に係る」と限定されています※2。要するに、財務諸表に示された数値が会社の状況を適正に示しており、虚偽記載となっていないかどうかです。
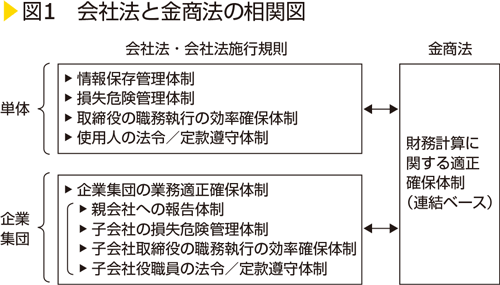
内部統制システムについて、会社法では、内部統制システムの評価は取締役と監査役との間で完結しているのに対して、金商法上は、経営者(取締役)と監査人との間の問題となっています。監査人は、経営者が評価した財務報告の内部統制システムの有効性の評価を行う際には、監査役の活動も統制環境の一環として評価します。他方、会社法上は、会計監査人の監査の方法と結果の相当性を判断して、監査役監査報告に記載します。会社法と金商法の間で、監査役と(会計)監査人との位置関係が逆転しているとの印象を持つ方もおられるかもしれませんが、どちらが法的に上位の位置にあるかを示しているわけではありません。その他、会社法と金商法の間では、規定の対象となる会社や罰則の有無等の違いもあります(<表1>「内部統制システム規定に関する会社法と金商法の対比」参照)。
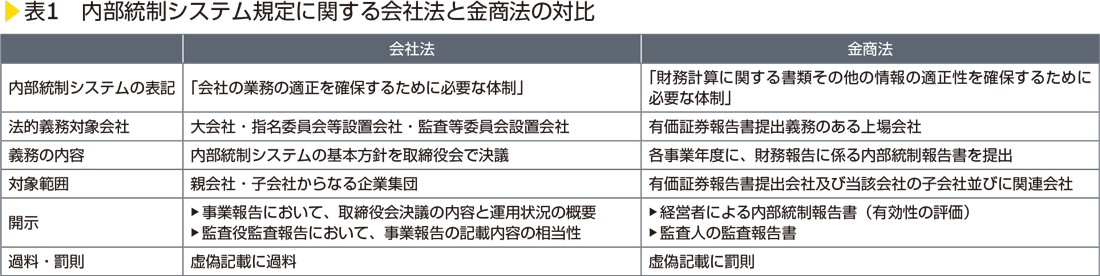
Ⅲ 会社法 と金商法の規定の交錯による問題点
1. 内部統制システムと時期ずれ問題
(1) 時期ずれとは
時期ずれとは、内部統制システムの開示に関して、会社法上の監査役監査報告が作成・提出された後に、金商法上の内部統制報告書が作成・提出されることにより、監査結果・評価のタイミングが異なることをいいます。3月決算会社の場合、監査役監査報告が作成されるのは、おおむね5月中旬であり、その後、定時株主総会参考資料の1つとして株主に通知されます。他方、内部統制報告書が監査人に提出され監査人が評価する時期は、おおむね6月中旬であり、両者で約1カ月の時期の差が生じることになります。また、単に、監査結果・評価のタイミングのみならず、最終的な評価者が、監査役と(会計)監査人とで異なります。
金商法の内部統制システムは「財務報告に係る」となっており、会社法と比較すると、その対象範囲が限定されていますが、金融庁の実施基準に示されているように、内部統制システムの評価手続は「全社的な内部統制の評価」が出発点となっており※3、評価対象範囲は両法で基本的には差がないと考えられます。
(2) 時期ずれによる問題点
内部統制システムの内容に関して、会社法と金商法との間に実質的な差がないとなると、事業年度における内部統制システムの評価に対して、会社法上の評価と金商法上の評価の整合性が問われることになります。実務的に、時期ずれの1カ月で評価が異なることに合理性が認められるのは、監査役監査報告提出後に発生した後発事象の場合が考えられますが、この場合でも、後発事象の発生のタイミングや内容の精査にも留意が必要となります。すなわち、一見、後発事象と思われる事象であっても、実際には、それ以前から発生の兆しがあったものであり、本来は会社法上の評価の時点において、十分に内部統制システムの相当性に疑義があると判断できる内容であった場合には、後発事象とされたとしても、その評価に差が生じることは基本的には合理性が認められないことになります。リスク管理として重要であり、会社の利害関係者(ステークホルダー)にとっても、とりわけ関心が高い内部統制システムの整備状況に対する評価が、時期ずれの問題や評価者の違いにより異なることになれば、当該会社の内部統制システムに係る法定報告書の信頼性にも関わることになります。
2. 時期ずれ問題とKAMとの関係
(1) KAM記載制度の意義
21年3月決算に係る財務諸表の監査から適用となったKAMは、財務諸表利用者に対し、監査人がどのような監査を実施したかという監査手続の内容に関する情報を提供することを通じて、監査の信頼性向上に資することを目的として導入された制度です。KAMは、監査人が独自の判断で選択・決定するものではなく、監査役との協議や、経営者との対話というプロセスを通じて実行されるものであり、監査人監査報告書が従来のひな型系の画一的なものから、KAM記載制度の導入によって、各社固有の情報が記載されることにより、投資者等に対する情報提供という点で大きな意義を持つものです。
これまでのKAMの主な記載事項としては、固定資産の減損、収益認識に対する不正可能性リスク、工事損失引当金、M&Aによる会計処理、繰延税金資産の負債認識や測定、システム障害、工場閉鎖関連の引当金、訴訟案件、偶発債務、重大な事故の発生等があります。
(2) 時期ずれ問題とKAMの問題
KAMの項目の中には、内部統制システムに関係する内容があります。例えば、システム障害、訴訟案件、偶発債務、重大な事故等は、内部統制システムが適切に整備されていれば、未然に防止でき得る可能性があります。すなわち、これらの事象が内部統制システムの整備の重大な不備に関係するとなると、金商法の制度であるKAMの問題にとどまらず、会社法上の問題にもなり得ることになります。
言い換えると、KAMは時期ずれの問題にも関係することになります。
Ⅳ 内部統制システムを巡る交錯問題への対応
1. 実務的視点
内部統制システムに関して、時系列的に会社法上の評価が金商法上の評価に先行する中で、監査役が、監査役監査報告において内部統制システムの構築及び運用状況が相当であると判断したにもかかわらず、監査人が経営者の内部統制報告書の内容の有効性に疑義を呈する評価をすると、監査役監査報告への信頼性に関わることになります。また、監査人が、経営者による内部統制システムへの有効性の評価に関して問題がないとの結論であったとしても、KAMとして選定された項目が明らかに内部統制システムの整備状況の不備に関係すると思われる項目が選択されていると、監査役監査報告の妥当性が問われる事態にもなり得ます。
このような事態を回避する監査役の実務としては、監査役監査報告をまとめる時点で、会計監査人との間で、全社的な内部統制システムの相当性に関する認識に齟齬(そご)がないか確認を行うことが重要となります。期末時点において、会社法上は、会計監査人から会計監査報告の通知を受領することで足りるところ、現実的には、監査役と会計監査人との間で、監査結果の説明及び質疑・意見交換を行う実務が定着しています。質疑等の際に、監査役として、内部統制システムの構築及び運用状況に関して相当であるとの結論に至っていたとしても、会計監査人に対して、金商法上の「開示すべき重要な不備」のような整備状況に大きな瑕疵(かし)がある場合はもちろんのこと、KAMの候補項目とその項目を選定した理由、さらには、事業年度を通じて、会計監査人の立場から、内部統制システム上、軽微な内容でも留意すべきとの印象をもった事象があれば、この点についても確認することが重要です。
可能ならば、監査役は会計監査人から会計監査報告を受ける際(3月決算会社であれば、5月中旬頃)に、内部統制報告書の評価(6月中旬頃)においても、現状の記載予定として特段指摘すべき問題がない旨の確認を得る実務が考えられます。会計監査人としても、後発事象の問題がない限りは、金商法上の内部統制システムの評価の前提となる全社的な内部統制システムについて、5月中旬には評価済みと考えられますので、会社法上の一連のスケジュールに沿って意見表明を行う実務は対応可能であると思います。その際に、監査役としては、会計監査人との間で、後発事象や期末後に是正される追記情報の可能性の有無、KAMの選定項目とその理由に関しても、意見交換を行っておきます。
時期ずれへの対応は、監査役と会計監査人との連携の実効性が具体的に問われることとなりますが、その基盤となるのは、期初・期中の段階から、内部統制システム整備の観点を意識した緊密な意見交換を実施し、課題や改善状況について意思疎通を図っておくことができる相互の信頼関係が醸成されていることです。
KAMの決定プロセスにおいて、監査人は監査役との協議が必要となっていますが、内部統制システムの評価についても、それ単独に対応するのではなく、監査役としては時期ずれの問題を意識して、(会計)監査人との協議に臨むべきです。
2. 立法論的視点
時期ずれの問題に対して、監査役と会計監査人との間の相互連携による対応は可能ですが、時期ずれの本質的な問題は、会社法と金商法との交錯にあります。両法を一本化することは、両法のそもそもの立法趣旨から考えて現実的ではない以上、部分的な改正によって対応することは考えられます※4。
時期ずれの問題を解消するためには、会社法上の株主総会参考資料の作成・公表時期と金商法上の有価証券報告書の作成・公表時期を極力接近させることが考えられます。内部統制報告書は有価証券報告書と一体として提出されますので、有価証券報告書の開示時期の前倒しが実務として定着すべきと考えます。有価証券報告書は、平成21年12月31日以降に終了する事業年度に係る有価証券報告書から、定時株主総会開催日より前においても提出は可能となりました(平成21年内閣府令第73号、開示府令17条1項1号ロ、19条2項9号の2)※5。しかし、実務実態としては、定時株主総会日以降の提出が圧倒的多数となっています。令和元年改正会社法で規定された株主総会資料電子提供制度の創設により、上場会社等では、株主総会開催前の3週間前、または株主総会招集通知の発送日のいずれか早い日までには、株主総会資料の電子提供措置を行うことが法定化されました(会社法325条の2)。この改正を機会に、有価証券報告書と内部統制報告書についても、株主総会前の極力早い時期に提出する工夫を行うことにより、時期ずれの問題は、かなり解消することが可能となります。
また、会社法上の事業報告、会計監査人監査報告及び監査役監査報告に、金商法上の財務報告に係る内部統制システムの評価の記載を何らかの形で義務付けることとなれば、時期ずれの問題を意識した実務対応となると考えられます※6。
Ⅴ おわりに
時期ずれの問題は、会社法と金商法の交錯から必然的に生じた事項ですが、内部統制システムの評価という会社の利害関係者に大きな関心がある内容に対して、監査役と会計監査人は、いっそう緊密な連携が求められることになります。しかも、時期ずれは、KAMにも関係する問題である以上、KAMに対する実務が定着しつつある現時点において、再度、原点に立ち返って監査役と会計監査人の連携実務に具体的に活かしていくことが重要であると思います※7。
※1 監査役と会計監査人との間の全体的な連携については、本誌2019年10月号 高橋均「監査役と会計監査人との連携の在り方と実務~ KAMの記載も見据えて~」2~6ページを参照。
※2 もっとも、金商法でも、内部統制の目的について「財務報告の信頼性」を非財務情報も含むとする改正の見込みである(企業会計審議会内部統制部会「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(公開草案)」(令和4年12月15日)2~3ページ。
※3 企業会計審議会(金融庁)「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」(令和元年12月13日)15ページ。
※4 時期ずれ問題以外に、計算書類と財務諸表、事業報告と有価証券報告書の間で類似の記載事項が多く、重複感がある書類は、どちらかに援用することが可能とすることも考えられる。この点については、関係省庁も問題意識を持っているようであり、2018年12月28日に、内閣官房、金融庁、法務省、経済産業省が共同で「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組の支援について(PDF)」(as of December 31.2022)を公表した。
※5 神田秀樹教授は、有価証券報告書を総会前に提出できるようになれば、有価証券報告書の財務諸表等をもって会社法の計算書類等に代えることが立法論として可能になる旨の意見を述べている。神田秀樹「二一世紀の六大課題と金融法制 第5回有価証券報告書の定時株主総会前提出への道」(書斎の窓No.685、2023年)3ページ。
※6 監査役監査報告の記載例として「事業報告に記載の通り、財務報告に係る内部統制については有効でないおそれがありますが、取締役はその改善に取り組んでおり、当期の計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類の適正性に影響が生じておらず、重大な取締役の善管注意義務違反となる事実は認められません」などが考えられる。
※7 内部統制報告書の実態として、2019年6月から2020年5月までの実績として、財務報告の内部統制システムは「有効ではない」との評価となった会社数は30社(全体の0.8%)であったが、これとは別に、同時期に113社が過年度に遡って、内部統制報告書を「有効」から「有効でない」に変更・訂正した会社があったようである(宮内義彦=八田進二=堀篭俊材『体験的ガバナンス論 ―健全なガバナンスが組織を強くする―』(同文館出版、2022年)160ページ)。本来であれば「有効でない」と訂正された会社の監査役監査報告の内部統制システムの相当性についても、あらためて検証され、必要に応じて過去にさかのぼって訂正もあり得るのかもしれないが、現行法では、その必要はないことになっている。会社法と金商法の連続性・関連性が法的に問われていないのは、時期ずれと同様の問題が存在しているといえよう。


